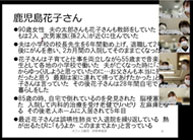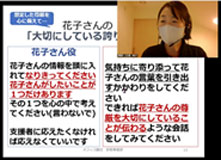第5回 社内研修(Web研修)
2022年10月31日 古城順子講師による社内研修 「本人の生き方を支える看取りケア」
オフィス藤田研修事業部 古城順子様を講師にお招きし、新入社員を対象に「看取りケア」に関する社内研修をおこないました。研修会は、新入社員に認知症ケアはもとより福祉の仕事の楽しさを感じてもらいながら、専門性を深めるための研修が進められました。
向き合うことが難しい終末期の支援の変化やご利用者の感情に寄り添うための支援について学びを深めました。事例として、Aさん75歳2週間前に脳梗塞発症、右片完全麻痺、嚥下障害、言語障害があり、鼻から経鼻胃管が挿入されてるご利用者を想定して検討しました。Aさんは、喉から胃のあたりまで違和感や痛みがあり、気持ち悪いから触ろうとし、頼みの左手は固定されています。注入時のギャッジアップが2時間以上続くと腰が痛みますが、「痛い」と言えず、ナースコールは押せない全介助の状態で、車椅子に乗せられてリハビリにいっています。2か月後は知らない施設に入居する計画が、専門職と家族の間で話し合われています。
古城先生は、「もしこれが自分だったらどうですか?」と問われ、「チューブが鼻に入っている状態で皆さんは生きていく自信がありますか?」と、自分がAさんだった場合を想像するように促されました。受講者からは、「自分の生き方や治療方針を自分で決める権利がある」「リハビリをするかしないか自分で決めたい」など、自己決定に関する意見が複数出されました。自己決定の経緯について、長い間、お年寄りだから、認知症だから、自分でしゃべれないからと考えられ、自己決定に基づかない支援が展開されてきたことを事例でご説明いただき、東京大学名誉教授の大井玄先生の説を挙げられ、社会は近い将来、亡くなる方のケアを想定せざるを得なくなり、どう亡くなるのか、最後までどう生きるのかが大切になり、どの様な状態であれ、自分で決めることの重要性が増す、と終末期における支援は自己決定が要になることを学びました。日本では、最期を迎える場所は病院が最多で、自宅・施設での看取りは極端に少ないのが現実です。社会情勢の変化に合わせて看取りの常識も変わりつつあり、身近に人の死、家族の死が普通にある時代になると、多死時代に向けた死生観の変化についてご講義いただきました。
支援の決定は、前回研修で学んだ、予め支援者の中にAさんと同じような気持ちを想像する予備的共感から始まります。選択は、自分ならと考える「同」の倫理、自分とは違う「異」の倫理を踏まえて決定します。受講者から出された意見は「同」の倫理で、この状態であってもまだまだ頑張って、孫の顔、ひ孫の顔まで見て人生を全うしたいと思っているかもしれない。と自分と違う価値観で想像するのが「異」の倫理になることをご説明いただきました。そのうえで、人格に備わる絶対的な価値である尊厳が護られる支援を提供すべきことを、事例を通して学びました。そもそも尊厳は、介護保険の理念において、「人間の尊厳の理念に立つ社会保障の体系として、高齢者の自立を支援し、人生の最期まで人間としての尊厳を全うできるように支援すること」と定義されています。尊厳の配慮は、自分のことは自分でできるように整える支援、その人が出来ることを奪わない支援、この二つの自立(自立・自律)に基づきます。尊厳への配慮として、自分ができることを許可なく奪われた時の気持ちを想像し、ご利用者が食事を摂っている時に1時間も2時間も掛かっている時にお手伝いさせていただく食事介助を事例に挙げて、適する声掛けを発表し合いました。適する食事介助は、まず予備的共感をおこない、「○○さん、お食事半分まで食べられましたね、頑張られましたよね」と声掛けし、「あと30分でお皿をさげないといけないんです、もっと食べて頂きたいので少しだけお手伝いさせて貰っても良いですか?」と尋ねて、「ご自分で食べたいんですけど申し訳ありませんね」とお伝えした時に、「うん、ありがとうね、頼むね」と言って下さった時の一連のプロセスを踏まえた支援です。「同」の倫理、「異」の倫理を踏まえたプロセスが自己決定であることをご教示いただきました。
受講生はAさんの気持ちを想像し、したいことや気持ちを受け止め、尊厳が護られる支援の重要性や言葉にして伝える難しさを実感しました。人生最後を迎えられるまでの目標や必要とされる関わりを学びました。看取りケアでは、自然に最期を迎えられる、同じ生活環境や人間関係の重要性を学びました。看取りケアは死期の近づいた人が、人生の最期を自分らしく穏やかに迎えられるよう、苦痛やストレスをできる限り少なくした生活の質を高める支援が重要です。ご利用者との関わりを振り返り一日一日を大切にしながら頑張っていきたいと思います。今回の全ての研修を通してご利用者への生活支援のあり方や、寄り添う為のケアの本質について幅広く学ぶことができました。古城先生、お忙しい中、数多くのご指導有難うございました。今回の研修で学んだことを糧に専門性の向上と、より質の高いサービス提供に努めてまいります。
※研修は受講者の体調・体温・接触管理・ワクチン接種・手指消毒等、室内換気も
徹底して行っています。