~対話という治療~
脳神経内科医師 黒野 明日嗣(くろのあすつぐ)先生
第4回 黒野先生による認知症ケア社内研修が開催され、「対話という治療」をテーマとしてご講義いただきました。
受講者は70名で、生活支援員、理学療法士、看護師、ケアマネジャー、相談員として認知症に関わっているスタッフです。


認知症の〇〇さん
認知症高齢者が増加していく中で起きている問題の一つとして、認知症と診断すると周りの方がその人の事を「認知症の〇〇さん」になってしまい、認知症のレッテルをすぐにはってしまうことがあります。認知症の方は言葉で伝える能力が失われることもあり、黒野先生も診断するときに躊躇してしまうことがあるそうです。今そのご家族に「お母さんは認知症です。」と言った方が良いのか、それとももう少し理解してもらってから伝えた方が良いのか迷う場面があったり、一度レッテルはってしまうとなかなか払拭することができないので、診断する側からすると認知症と診断する時は緊張感があるなど、実体験のお話を聞くことができました。
認知症の知識が増えるとコミュニケーションや支援の方法も変わり、アルツハイマー型認知症は記憶出来なくなる病気なので「さっき言ったでしょ」という声掛けではなく、昔の習慣や対象者の人生(生活背景)というものを理解して接することが大事だと気づくことができます。
レビー小体型認知症は幻視や見間違いが多いので、その原因となる事を取り除けば改善することが出来ます。例えばハンガーに服を掛けて壁に掛けていると、人が空中に浮いている状況に見えて不安になりますが、その服を取り除くと見間違いは起きなくなり、その後は安心して生活をすることが出来るようになります。
脳血管性認知症は脳梗塞や脳出血など脳の一部が損傷し、遂行機能障害といい計画を立てたり、順序立てて実行することが困難となります。

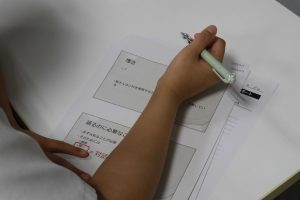
今回のように勉強会を開催し、組織として認知症に関する知識を増やしていくことで、認知症の方も安心して生活を送れる環境が整うことになります。
医療・福祉に携わっている方の考え方で強いのが、何かをしてあげたいという思いから、つい介入してしまうことが多いです。実は何もしないで見守る・観察するという事も重要な介護であり、その人知るために必要な時があります。認知症ケアは人としての理解が求められます。どうしてそのような行動をしたかったのか、なぜそのような選択をしたのか、その方の生活歴や過去の出来事を思い返して自分なりに解釈し、ケアを考えることが大切です。
話が変わり黒野先生から「皆さんはいろんな勉強をしていますが何のためにしていますか?」と参加者に質問がありました。知識は何のために向上して、活用し実践するのか、その意味を自分自身が分かっていることが重要です。また、私たちは考えて仕事をする際、行動指針であるニコニコタウンきいれ~心にいつも7ヶ条~を心に秘めて仕事を行わなければなりません。
- まず主人公は、利用者であるお年寄りだと認識すること。
- リーダーシップ・メンバーシップがそれぞれ確立していること。
- 職員全員が、お年寄りの言動に関心を持ち、耳を傾ける態度を身につけること。
- 職員全員が、お年寄りを受容し理解しようとする気持ちを持つこと。
- 職員全員が、情報を共有できる体制を普段から作っておくこと。
- 情報の収集・サービス内容の検討は、ケースカンファレンスを通して確認すること。
- ケースカンファレンスの際は勿論のこと、あらゆる場面で一人ひとりの職員の考え方や発言が大切に扱われること。


聞く・話すということ、向かい合って話し合うことが対話であり、会話と声掛けとは異なります。会話は複数の人が互いに話をすること。声掛けは声をかけること、挨拶をしたり安否を問うたりすることです。
認知症の方が家族と同居しているのに、寂しいということがあります。家族は会話をしていますが、本人は発言出来ないので返事をすることしかできない。その環境は1人取り残されているので寂しいのです。直接「テレビを見る?」などその人に向かって話をして、その人の返事を待つ事が対話なんです。対話とは向かい合って話をすることなので、時間が無いと出来ないというところが欠点です。対話ができる2人だけの空間、静かな場所、腰掛けて話をするなど、環境的な配慮や目線を合わせて、今、対象者の話を聞くこと・話すことに意識していることを伝え、対象者が話しやすい空間をつくることが大事です。また、対話をしてもらえるよう、対象者を理解する気持ちや対象者に自分のことを知って頂くことも大切です。そのような環境的配慮、意識をもって、対話をすることによって、お互いに気づきがあり、それによって新しい関係性が持てることが認知症ケアになります。そのためには、対象者がどのような方なのか、援助者としてどのような姿勢で対話に臨むのか事前の準備も大切になります。また、対象者のことを知ろうとするには、自己開示し合う必要があり、対話し続けることが重要であることを教えて頂きました。話すことが難しくなった重度の対象者においても、話しかけ、表情から返事を類推すること、うなずくまでの時間・間隔からその意図を推し量れることができるかもしれない、「対話」でないと気づくことができないことを教えて頂きました。
それを可能にするには業務改善を行い、対話できる環境を整えなければなりません。業務を改善することは何のために行う必要があるか、目的を明確にして取り組む必要があります。そのためには、スタッフ間での目的の共有も重要となります。
組織の価値は職員の中で考える人がどれほど多くいるかによって変わります。失敗を恐れずに色々なことにチャレンジする事が重要で、答えを出すことだけに縛られずに、体験を次に活かせるように取り組んでくださいと激励のお言葉を頂きました。認知症は対話を最も必要とする疾患であることを理解し、「何のために対話をするのか」という問いを持ち続けることが大事であることを教えて頂きました。職員で考え、チャレンジしたことを共有し、組織の価値を高めて、質の高いケアにつなげていきたいと思います。

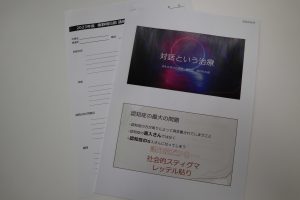
黒野先生、今回も本当にありがとうございました。 次回もよろしくお願いします。
※研修は出席者の体調・体温・接触管理・ワクチン接種・手指消毒・室内換気を徹底し行っております。








