第3回 リーダー社内研修「身体拘束・虐待」
2021年12月20日 古城 裕喜 講師による社内研修
第3回 リーダー研修において「身体拘束・虐待」の知見を深めました。
最初に、都道府県に報告される高齢者虐待件数は、全国的に増加しています。鹿児島県の介護施設従事者等における高齢者虐待件数は、令和2年度7件の虐待判断を受けていました。虐待に至る福祉現場のメカニズムを考察し、問題が起きる背景と要因、根拠のある対策とケアの手法を学びました。
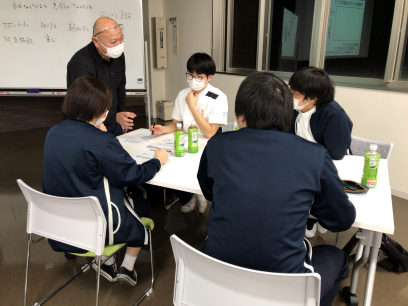
古城講師は「高齢者虐待・身体拘束は何故ダメなのか?」と問いかけ、先入観や前提知識を抜きにグループワークしました。私たちが持つ倫理観を振り返り、問題が起きる背景と要因を検討します。
スタッフからは、「なんでダメって…。」と思わず言葉に詰まる場面や、「虐待や拘束には4つの弊害がある」と、虐待から生じる事象を問題視するスタッフがいました。参加者の持つ倫理観に大きな違いがあることを認識しました。
古城講師は自由権に基づき問題が起きる背景と要因を解説いただき、自由が奪われることの弊害を、事例を挙げてご教示いただきました。

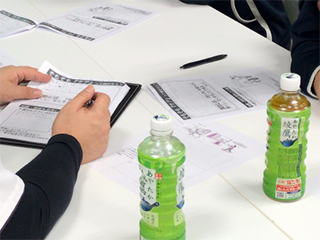
そもそも顕在化した虐待の前には、非意図的な虐待があります。虐待に発展する要因を検討すれば、不適切なケアと未熟なケアの存在がみえてきました。ケアの中身を分解し目的を理解することで、現場スタッフに分かりやすく伝えられることを学びました。
古城講師は、マズローの欲求に触れ、「援助者は利用者の安心・安全ばかりに着目しすぎていないか?」「生きがいなどの精神的欲求をおろそかにしていないか?」と問題提起されました。注意すべき支援のバランスについてご教示いただきました。

現場には、利用者から暴言等を受ける場合があり、表面的なかかわりでは利用者の行動の真意に辿り着くことはできません。援助職は、自身における意識の志向性や感情の癖を正しく知り、上手く付き合っていく「難しさ」「大切さ」を認識しました。
研修を通して、虐待・身体拘束に至る社会的背景を認識し、援助者自身が利用者ニーズを正しく捉える重要性、スタッフ教育における言語化の大切さを学びました。本日の研修内容を踏まえて利用者ニーズと向き合い、良質なケアを行っていきます。
今回は年内最後の研修でした。古城講師、お忙しいなかご登壇いただき、ありがとうございました。令和4年もよろしくお願いいたします。
※研修は講師、参加者の体調・体温・接触管理・ワクチン接種・手指消毒等、室内換気も徹底して行っています。
参照:鹿児島県「高齢者虐待の状況の公表について」
(https://www.pref.kagoshima.jp/ae05/kenko-fukushi/koreisya/gyakutai/koureigyakutaikouhyouh25.html,2021.12.23).








