第2回 新入社員研修カリキュラム Web研修
第2回 新入社員研修カリキュラム(2022年6月7日)Web研修
第1部 介護現場に就職して感じた事
新入職員は職場に慣れるまで毎日緊張の連続と思います。特に初めての職場環境で働く場合、仕事の内容や職場の雰囲気に馴染めるのか、利用者様との関わり方にこれで良いのかと不安を感じる事も少なくありません。今回のカリキュラムでは新入社員が就職し感じた事を発表してもらい、参加者全員でそれぞれの思いを共有し、さらに学びを深める講義となりました。
生活支援において、「利用者様に対して支援させて頂いていますが、生活援助技術の難しさ感じます。相手の方の気持ちを思うと、自分の技術がこれで良いのかと疑問に思うことがあります」との声に田中教授は、「若い私たちは発達段階で成長していきますが、高齢者は逆に衰えていきます。若い時に比べて体は硬くなり手伝いを必要としますが、支援はご利用者様の難しい所、出来ない所を行う事が大切であり、何でもかんでも支援する必要はありません。親切や心配をするのは良いですが、余計なお世話は本人の能力を奪ってしまい自分らしい生活が送れなくなる恐れがあります」とご指導下さいました。
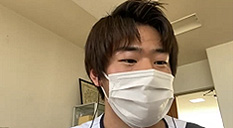

支援サービスの特性では、各事業所の目的や支援サービスの違いがあります。
利用目的やその違いについて、分かり易くお話しして下さいました。デイサービス?デイケア?と普段耳にしますが新入社員にとっては、何が違うのかという疑問に感じることがあります。それぞれの特性の違いを理解することで、専門職としての役割と必要性を学ぶ事が出来きました。
言葉の意味を一つ一つ理解しながら、新入社員たちも真剣に講義を受けていました。
第2部 介護現場に就職して感じた事
高齢化の進展とともに、認知症の有病率は年齢と共に高まることが知られています。認知症とは、「何らかの脳の病的変化によって、認知機能が障害され、それによって日々の生活に支障があらわれた状態」と言われています。
生活支援では利用者様が「家に帰りたい」「物を盗られた」など様々な訴えが見られます。また、話が通じる方もいらっしゃれば、意思疎通が難しい利用者様もいらっしゃいます。そばにいて利用者様へいくら話しかけても、相手の方が私に話しかけていると理解しない限り、その声は相手に伝わりません。では、会話が上手く行く方法として、田中教授より「目を見て話す事で相手は安心する」また「スキンシップを図り、アイコンタクトをとる事により落ち着かれ話を聞いて下さる」と介護者が留意すべきポイントをご指導くださいました。
自身の行いに問いをもつこと、教授からのすぐに実践に移すことのできる回答が
着実に新入社員の成長に繋がっています。

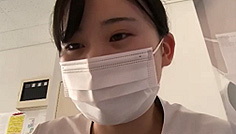
介護の楽しみは出来ないと思われていたことが、案外出来るようになったと気付いた時に楽しくなります。会話が広がり、相手との信頼関係が取れて意思疎通がうまくいくと仕事も楽しくなります。更に、仕事が楽しくなると利用者様との関わり方も増えていきます。これが仕事のやりがい、生きがいに繋がります。
現場に出てから約2ヵ月が経つ新入社員の皆さん。
より現場目線からの質問が増え、早い成長を感じます。
まだまだ、講義は始まったばかりです。福祉の現場で働く専門職として、介護の深さを知り、悩みに向き合いながらより大きく成長していきましょう。
田中教授、本日はありがとうございました。








