第5回 新入社員研修カリキュラム Web研修
第1部 「介護の本質・定義」
今回の研修は「介護の本質」についてご講義いただきました。
介護とは、何らかの困窮があり、困窮と感じる人がいて初めて発生します。客観的には困難な状況にあるように思えても、本人がそれを困窮と感じない場合は、いわゆる「介護」は発生しません。見方をかえると、困っている人がいても、困っていると感じなければ、介護という関係性は生じません。
このことを田中先生は事例でご説明くださいました。片足を骨折し、杖や松葉杖で歩いているとします。自分で歩いている場合は、「ここを手伝って下さい」という本人からの訴えが無いと介護は発生せず、足を骨折しているようであり困っているようにみえても、他人をあてにするほどでない場合は、関係性は生まれないとするのが「本質的な介護」だと学びました。
身体的に何らかの病を持っている人が、自分では病と思わず、医師に診察を受けに行かないのと同じであると知りました。病は存在しますが、本人が病気と思わない限り受診することは無く、治療という関係性は生じないのと同じだということです。
たとえば、38℃の熱がある方がいるとします。熱があり少し頭が痛い程度で身体に異常が感じられない場合では、「病人」ではあるものの、病院受診しなければ「患者」と「医者」との関係は生じません。介護も同様で、障害があり、その障害を本人が「困った、誰かの手が必要だ」と求めない限り関係は生じない、介護とは関係性のもとで成り立っていることを医療と比較して学びました。
 田中先生は、介護の関係性とボランティアとの違いについて、違いの意味を理解することが大切だといわれ、困りごとの手伝いが主体のボランティアと、専門職が行う生活支援との違いをご講義いただきました。ボランティアで行ったことには責任は生じませんが、専門職は責任を負います。ここに大きな違いがあり関係性も異なります。専門職としての関係性は、誰かの手を借りなくても、ご本人が自分で何とか生活を送れるように、その方に必要な適切な支援が何処にあるのか、利用者様の困っている部分を把握し、必要な支援を実施することだとご指導いただきました。
田中先生は、介護の関係性とボランティアとの違いについて、違いの意味を理解することが大切だといわれ、困りごとの手伝いが主体のボランティアと、専門職が行う生活支援との違いをご講義いただきました。ボランティアで行ったことには責任は生じませんが、専門職は責任を負います。ここに大きな違いがあり関係性も異なります。専門職としての関係性は、誰かの手を借りなくても、ご本人が自分で何とか生活を送れるように、その方に必要な適切な支援が何処にあるのか、利用者様の困っている部分を把握し、必要な支援を実施することだとご指導いただきました。
田中先生は介護サービスについてご説明くださり、本人が困っていても、何らかの依頼がないと関係性が生じないことを事例でご説明いただきました。病気や骨折、或は 障害や認知症等を患い、そのうえ本人や周りの家族の手に負えなくなり、何らかの支援を必要とした時に初めて介護関係が成立することを学びました。
第2部 「生活支援ということ」
田中先生は、生活支援、福祉というのは生活から命を支えることであり、命を支える重さは医療と変わらないことを事例でご説明いただきました。食事が食べられない人をそのままにすると体調は悪化し生活が困難になります。どのようにしたら利用者様が食事を摂ることができるかを検討し、ご家族様と話し合う必要があります。医療支援でみると、状況に応じて点滴を行なうなど、適する医療を検討する必要があります。生活支援員は、上手に口から経口摂取できるように、必要になる支援を検討し、その人らしい普段通りの生活を送ってもらえるように検討することになります。医療は適切な医療支援を提供し、生活支援員は、利用者様と適切に関わり、その人らしい生活の「快」をみつけて、生活と命を支える支援を提供する役割があることをご教示いただきました。
一方支援は、多くの職種で関わるスキームが大切で、生活を楽しめるチームケアを検討すべきです。利用者様に目標を持ってもらうことで、「頑張ってみよう」という意欲が生まれ、生きがいにつながることが期待されます。スモールウインを積み上げ、希望の実現を目指した成功体験が得られる生活支援が必要になるとご説明いただきました。

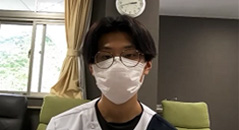
人には喜怒哀楽があり、喜び、悲しみ、苦しみをあわせて人生です。利用者様も同じで、それぞれに合った喜びとは何かを見つけ出し、「ニコッ」とした笑顔を引き出すのが生活支援員の仕事だとご教示いただきました。
今回のカリキュラムは、介護の本質をテーマに、多くの知見と考え方をご指導いただきました。普段の関わりには多くの意味が含まれることが理解できました。利用者様の生きがいの実現に向けた生活支援が行えるようにこれからも頑張って行きたいと思います。
田中教授、本日はありがとうございました。
コロナウィルス感染対策を考慮し、リモートでの研修を開催させて頂きました。








