第8回 新入社員研修カリキュラム Web研修
第1部 総合技術としての狭義の介護
介護技術は,広義でみると他者理解の技術を含む哲学的な意味合いがあります。問われるのは、認知症等により事理弁識が不足、或は、欠く対象者ニーズを受容するチカラです。一方、狭義でみると対象者ニーズに応じる総合技術であり、高い専門性が問われます。いずれも選択肢が重要であり、判断基準を用いる「位置づけ」と普段から用いている「価値づけ」を事例を通して学びました。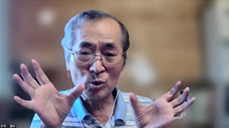
一般的「価値づけ」は、無意識もしくは簡単に選んでいる選択になりますが、絶対的「価値づけ」では、二者択一が問われる難しい選択になります。たとえば、食堂でメニューを見て注文を決める時、「今日はお金がないから安い定食で我慢しようかな」、或は、「今日はお金があるから鰻でも食べようかな」など、数ある選択肢から選ぶのが一般的「価値づけ」で、多くの場合は深く悩むことはありません。一方、人生のパートナーの選択など、絶対的「価値づけ」では選択が難しく悩みます。一般的「価値づけ」を行うには、数ある選択肢の中から自分に都合のいい選択をします。その都合にあたるのが「価値づけ」で、日常生活ではそれほど考えずに行動します。この行動が「分かっちゃいるけど止められない」といった刹那行動に繋がり、普段しない選択をした時、後で後悔するものです。あれか・これかと選択するのは「選考価値」に基づき、「こうしないといけない」と二者択一が求められる選択は、「絶対価値」に基づいて行われます。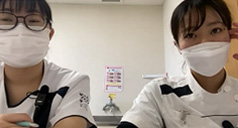
介護技術の価値は、単純な比較で介護を決めるのではなく、狭義の介護として、価値の選択肢を十分検討できる総合技術であることを学びました。
第2部 価値・理想・道徳
二者択一の「絶対価値」に基づく選択には「理想価値」が問われます。「価値」に紐づく「理想」や「道徳」は時代で変化し、たとえば、独身時代の20歳代の「価値づけ」では自分で好きな事をする自由度がありますが、結婚した30歳代の「価値づけ」では2人の生活が背景にあり、生活を円満に築くための我慢という選択が求められます。百人百様の人生があるように、それぞれの価値を理解することが基本になります。対象者がどういう人生を送りたいのかを検討するには、模範解答は無いことを念頭に置き、対象者がこれで「良し」と思った生き方に寄り添い、対象者の生き方を尊重し、残りの人生を楽しんで頂けるように関わることが大切です。今、寂しい不幸せだと思っている対象者が、「これまでの人生はそうでもなかったんだ、私のこれまでの人生はそれなりに幸せのある人生を送ってきたんだ」と気づき、「残りの人生も頑張ろう」と感じてもらうことが介護の専門性であると田中先生よりご教示いただきました。


「人は時代の子」で、時代的価値観に左右されます。本来、人を助けるはずの組織や集団でも争うように、「理想価値」は「選考価値」と違って「道徳性」という普遍的な特性を持っています。「人が理想価値を持つ場合、自分自身と同様に他者をも審判するのである」このことを踏まえる必要があります。介護の関係性でみると、対象者の価値観に寄り添い、「人生はその人のものであり、その人がこれで良いと思う人生に近づける」のが、介護の関係性における哲学となります。大切なのは、専門性の奥にある多くの学びを追求し深く関わることです。繰り返すうちに自分のやるべき介護が見つかり、専門職としての成長に繋がると田中先生よりお話がありました。
バイスティック7原則では、人間は個人として扱われたい欲求を持っています。これが「個別化」です。私を見てもらいたいという欲求もあります。ひとり一人に違いがあるように、それに応えられる対応技術はそれぞれ異なります。人は生まれながらにして人から受け入れられたい欲求があり、専門職の介護には、受け入れるチカラが求められることを田中先生よりご説明いただきました。
今回のカリキュラムで、介護の関係性の基礎を田中先生よりご指導いただきました。学びを追求し専門職として成長できるよう研鑽したいと思います。
田中先生、本日はありがとうございました。
コロナウィルス感染対策を考慮し、リモートでの研修を開催させて頂きました。








