第12回 新入社員研修カリキュラム Web研修
第1部 感情がコントロール出来ない認知症高齢者との関わり
新入社員からの質問「怒っている時に発せられる言葉の意味」への回答として、認知症高齢者の感情についてご説明いただきました。
田中先生は、いわゆる「怒っている」とは、主に認知機能と感情のコントロール機能の低下が影響し、身の回りのことや今生じていることが把握でき難くなることが背景にあると言われ、何らかを嫌なこととして誤認し、「怒る」が現れるとご説明くださいました。
誤認から生じる言動「怒る」は訂正不能で、真実でないことを真実と思い込み、嫌なことから身を守る回避行動になります。「どうしたの」と尋ねることは避けるべき対応になり、尋ねられると、認知機能の低下と感情のコントロール機能の低下から、説明できないことに苛立ちや怒りを感じ、益々興奮し、関係性が悪化する傾向があります。原因がわからない「怒る」の適切な対応は、「理由を知ろうとしない」「余計なことは言わない」「言っていることに耳を傾ける」になります。怒っている時の言葉が、その人の本心でないことを理解し、日常的に発している「その人なりの言動」を理解することが重要になることを学びました。
適切な観察を行うと、「あれ、この人いつもと違うな、何故だろう?」と気付き、質問を変えながら相手の反応をみると、「その人なりの言動」を紐解く情報が得られます。情報を活用して「今、こういう怒り方をしているんだけど、それが本心かどうか、ひょっとしたらこれが原因ではないか?」と気付けることを、事例を通してご講義いただき、普段の関わりの重要性を学びました。


一方、なんとなく苦手な人は近寄りづらく、苦手意識から近寄らないでいると情報が入らず、プロとしての専門性も得られません。「あっち行け」「お前の顔も見たくない」といわれても、普段の関わりが十分でないと関係性は難しくなります。「あの人は苦手だからなるべく関わりたくない」から呼ばれても早くその場を離れようとしていると、自分の気持ちが利用者に伝わり、利用者から嫌われ関係性が悪化します。他者理解、自己理解が重要であり、普段の関わりの中で、どういった所に興味があって、どういった時に冷静さを欠くかを理解すると「ひょっとして、冷静さを欠く言動はここにあったのかな」という推測ができるようになります。推測に基づき言葉を返す流れを介護過程といい、介護の現場で行う介護プロセスの流れを学びました。
行動は意図的であるべきです。「あなた何故、今こういう言い方をしたの」と尋ねられたら、冷静に「私はこういう理由でこのような言い方をしました」「このような行動を取りました」と、丁寧に説明する必要があります。「えっ、私そんなこと言ったの?」というと素人です。自己覚知して、頭の中で整理して冷静に会話すべきであることを学びました。
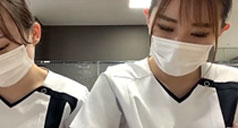

第2部 「サービス業としての介護」について
一次産業とは、自然に働きかけて手に入れる農業や漁業になります。二次産業は加工品や工業製品になり、三次産業はサービス業になります。教員や医者、介護も三次産業になり、ほとんどの職業がサービスで成り立っています。サービス業としての介護は、一般的なサービス業と共通する部分がありますが、サービスの本質は両者では大きく異なります。
一般的なサービス業は、お客様が望むことに応えるサービスであり、数あるサービスの中から選ばれる必要があります。コンビニに優しく丁寧な店員さんがいたとしても、買い物をしなければそのお店は潰れます。ガサツな店員でも、品揃えが良く商品が売れれば、お店は繁盛します。一般的なサービス業は、商品やサービスを買ってもらい売上が伴わなければならず、そこに本質があります。売上を伴わないサービスはさほど重要視されず、売上という結果が重視されます。むしろ売り上げを伴わないサービスはできるだけ省きたいのが本音です。利潤を追求する企業にとっては当然で、お客様に選ばれることで成り立っています。ゆえに、サービスの範囲はお客様が納得できる範囲に留まってしまいます。
一方、介護の場合は、サービスの質で売上は増減せず、利用者に必要で本当に喜んでもらえるサービスを提供します。サービスの中身と売上は福祉的サービス業では関連しません。どんなサービスを行っても、得られる対価は一定であり、要介護5の利用者が施設サービスで25万円のサービスを受けたとすれば、施設に25万円入ります。良いサービスを提供しても、さほど良くないサービスであっても売上は変わりません。売上が変わらないからといって、サービスを減らしてもいいかというと、それは福祉的なサービス業の本質ではありません。売上は伴わないが、プロとして利用者が喜んで貰えるためにどうするかを考え、よりよいサービスを提供する必要性があります。福祉的サービス業の本質は、利用者に満足いただけるサービスを考え、最適なサービスを提供することです。サービスの範囲は利用者が納得できる範囲を超えることもあり、提供されるサービスそのものに本質があります。福祉的サービスではサービス提供過程が重要視されると田中講師よりご教示頂きました。


田中教授、本日はありがとうございました。
コロナウィルス感染対策を考慮し、リモートでの研修を開催させて頂きました。








