第14回 新入社員研修カリキュラム Web研修
第1部 「ご利用者の主体性を尊重する」について
前回の講義で質問に挙がった、日常的に介助の必要なご利用者が、「どうしても自分でやりたい」といわれたら、どの様な判断が相応しいのかを、事例を通して学びました。
田中先生は、専門職の支援として、予見可能性を挙げられました。ご利用者の現状を「危険」と判断する、危険の緊急性を「高い」「やや高い」「比較的高くない」に判別し、怪我等の発生を予見した支援、訴えが本当であるかの判断が重要になるとご説明いただきました。支援者によって危険の判別は違い、非常に危ないと感じる支援者もいれば、これ位なら大丈夫と判断する支援者もあり、支援者の判断能力が重要になると事例を通してご講義いただきました。
一方、ご利用者に強い意欲があると、怪我をさせない為の支援が歩行能力を低下させ、相応しくない支援になる場合あります。「やや高い」と判別したら、「ふらつき」にいつでも対応できる位置で見守ることで、ご利用者の強い意欲に寄り添いながら危機を回避することを検討すべきです。場合によっては、「少し歩いてみましょうか」と声掛けし、ご利用者の脇を支え、膝折れした場合でも身体を支えながらフォローする方法もあります。危険の判別と対応方法で支援は異なり、ご利用者の日常の状態把握と実際にご利用者がどの程度できるかを十分に理解した支援が重要になるとご教示頂きました。

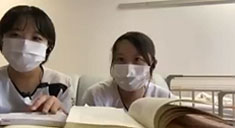
「主体性を尊重する」主体性とは、自分の意思で生活を選択・決定することであり、障害の有無に関わらず、主体性が尊重される支援を検討します。誰しも自己決定を行いながら主体的に生活すべきですが、物事の判断が出来ない状態になり、危険の緊急性を「高い」と判別せざるを得ない場合では、支援を変更する場合があります。その様な時ご利用者は、自分らしい生活を送りたいにもかかわらず支援が変えられ、理由が分からず反発することがあります。生活支援員は、なぜ反発されるのかを考え、自己実現を叶えられる支援を探っていきます。ご利用者を深く知っていると、必要な支援に気が付くことがあります。これが自己覚知であり他者理解の基本になります。基本を踏まえない支援であると、自己満足に終わる恐れがあり、注意すべきです。主人公はあくまでご利用者であり、主人公が喜んでもらうにはどうすれば良いか、ご利用者の立場に自分を置き換えて関わることが重要になるとご説明いただきました。


第2部 「平等イコール均一という誤り・公平」について
田中先生より、施設ケアでは、平等性のもと、全てのご利用者に同じサービスを提供する傾向にあると、問題提起されました。
一人ひとり、感じることも思うことも異なり、満足度も好みも違う、同一のサービス内容が満足度を高めるとは限らないことを、事例を通して学びました。
少ないサービスで満足するご利用者もいれば、たくさんのサービスがないと満足できないご利用者もいる。基準を誰に合わすか、或は、何処に置くかが重要になるとご講義いただきました。


一般的な事業で提供されるサービスでは、要望全体の平均を捉えて、同一サービスを提供すれば「それは頼んでいない」という苦情が生じます。福祉の考え方では、お昼ご飯を提供する時に、ご飯の量が人によって異なるように、「私は少ない量で大丈夫」または「私は大盛りでないと足りない」という要望に合わせることが平等になります。普通の社会では、ここにみかんがあります。「私は普段は1個あれば足ります」「私は5個あれば足ります」という訴えに、1個と5個で平等になりますか? 「今は1個だけど、あとで食べるからきちんと3個3個に分けて下さい」となります。一方、福祉ニーズでは、今困っている中身に対しての訴えで、ご飯の量は、それぞれの基準に合わせることが平等となります。後々ご飯が欲しいから出来るだけたくさんご飯が欲しいなどの訴えは、ニーズを越えた欲望となります。福祉に携わる生活支援員は、ニーズの意味をきちんと理解すべきだと問題提起されました。
公平について、公平とは均一に対応するのでなく、同じように接するという意味でもありません。介護保険において、ニーズへの対応は介護保険下での要介護度に違いがあるように、提供されるサービス量に違いを設けて公平と考えています。同じように行うのが平等で、公平とは異なります。公平・平等は、今までの経験をそのまま福祉に当てはめようとすると、間違った平等・公平になってしまいます。ご利用者の関わり方で考えると、Aさんへの関わり方とBさんへの関わり方は、同じ内容の関わり方ではないが、関わった回数を同じにすることで、公平を担保することが重要だとご説明いただきました。
ご利用者を把握した平等が大切になります。最初から親しみを込めた話し方をすると、相手によっては気分を損ねてしまうこともあり、丁寧な言葉遣いで、関係性が少しずつ出来た段階で、親しみのある言葉を使い、会話を繰り返すことが必要になります。関わる内容を同じにするのでなく、関わる手法や技術を変え、そのうえで平等を意識することの大切さを学びました。
今回のカリキュラムにて、主体性・公平・平等ついて田中先生よりご指導いただきました。ご利用者との公平・平等な接し方を改めて振り返る講義となりました。ご利用者の訴えに、ニーズの理解と欲望の違いについて学ぶことが出来ました。今回の講義で学んだ知識を活かし、ご利用者に喜んで頂ける支援を追求していきたいと思います。田中教授、本日はありがとうございました。
コロナウィルス感染対策を考慮し、リモートでの研修を開催させて頂きました。








