第15回 新入社員研修カリキュラム Web研修
第1部 研修の総括
田中安平先生による新入社員研修は最終日となりました。生活支援の専門性と援助法を総括し、今後の抱負を発表しました。ご利用者との接し方が、研修前と比べてどのように変わったかを話し合い、今後の抱負などを発表してもらいました。そもそも、寄り添った介護とは、ご利用者の価値観を理解した支援のことです。この価値観は他者理解を踏まえて得られるもので、異なる人の価値観を理解するには、自分の価値観を捨てて、先入観の無い状態で相手の訴えを受け入れることから始まります。新人スタッフからは、目先の言動で判断せず「あっ、この人はこのように思っているんだ」と、事実として受け取るスキルを習得できた、との意見がありました。たとえ、自分の価値観と違っていても相手の価値観をありのままに受け入れる事で、その人の望む希望が理解できることを学んだようでした。
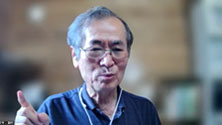

生活支援で大切なのは、ご利用者の思いに気遣いできるかどうかで、このことが価値ある支援の基礎になるとご教示いただきました。介護は実践学で、思いを実践に移すことで価値が生み出されます。頭の中で理解していても、行動に移せなければ介護ではありません。それぞれの支援に各々が実践し、力量を高め続けることが専門職の役割だとお話しになりました。
ご利用者が満足し、生きがいを見出せるサービスを提供するには、ご利用者のでき来ない所が何処にあるかを、観察し気付くことから始まります。支援者の行動や表情は、ご利用者の行動や表情に反映し影響します。顔をみて話しかけると「この人、私をみてくれているんだ」「私を理解してくれているんだ」と感じてもらえ、ご利用者に支援者の感情が伝播します。


ご利用者の訴えに反応せず、支援者が無視をしたような行動を取ると、「自分には興味がないんだ」と思われてしまいます。同じように声掛けしても反応が無い場合、「どうして私にはそっけないんだろう」と感じます。お互いの事をよく知るには、今、ご利用者はどんな顔をして、私の声掛けにどのような反応や行動をしているのかを観察することが大切です。非言語的コミュニケーションも重要です。言葉に現れない身振り、手振り、態度を観察し、「私はあなたの事を見ていますよ」「あなたの事が好きですよ」と、非言語的コミュニケーションで会話すると信頼関係も深まることをご講義いただきました。田中先生より注意すべきこととして、現場での忙しい行動を挙げられ、相手はどう感じるでしょうか?と問題提起されました。そのような環境で、ゆっくりと話をしたいと思いますか?と話され、ご利用者は支援者の言動に反応していることを学びました。
第2部 「これまでの研修を振り返り各自の今後の抱負」について
福祉は、ご利用者の幸せの為に存在し、満足や幸せの共有だといわれます。福祉の仕事を一言でいうと、幸せのおすそ分けです。ご利用者の幸せは、生きがい、満足、喜び、自己実現に向けた自分らしい生活の中にあり、できる事ができなくなった時、どうしたら満足や喜びを感じていただけるかを考えることから始まります。できない事を少しずつできる事にし、「今日はありがとう、助かった」「今日は良い日だった」と、感じてもらえる関わりを模索することが大切になります。ご利用者の喜びは支援者の喜びでもあり、これが福祉の原点になると田中先生よりご教示いただきました。
ご利用者の生活を支えるには、ご家族抜きでは叶いません。コロナ禍の感染予防対策で、なかなか面会もできないないケースを事例に挙げられ、ご利用者もご家族も寂しい思いをしていることに触れられ、面会に代わる方法をご家族を巻き込み検討し、窓越し面会や携帯電話のテレビ電話機能で代替するなど、関係者を巻き込んだ取り組みを模索し続ける重要性を学びました。今回の研修で学んだKJ法で、関連のあるものを言語化し、グルーピングすることで、どこに課題があるのかを探り、解決法や新たな気付きにつなげ、実践に移すことが福祉の基本になることを学びました。専門職として、これからも自分を磨き続け、よりよい支援を目指し続けることの重要性を田中先生よりご教示頂きました。


研修を通してスタッフの感想
「研修を通して、介護とは何か、介護の本質についてどういうものなのかを理解する事が出来ました。ご利用者様のニーズに対して、平等について全てのご利用者様に同じことを行うのではなく、個別に必要な支援を行う事を理解する事が出来ました。」
「利用者様に寄り添った生活支援員になりたいです」
「自己覚知をした上で、役者になり切る先生の言葉が印象に残りました。自分自身が変わって行けば利用者様との対応や反応に変化がある事を学びました。」
「自分の価値観で行動しがちですが、相手の価値観に寄り添って配慮する事で、
一人ひとりに合った介護サービスを提供出来る事を学ぶ事が出来ました。」
「利用者様の今までの生活について、培ってきた価値観を自分が理解した上で利用者様の望む行動や将来的な生活を行う為の、生活支援の必要性を学ぶ事が出来ました。」
「全ての利用者様に、満足して頂けるサービスを心掛けて積極的に利用者様と接して、一人ひとりの生きがいを見つけて頂ける様に取り組んでいきたいです」などの多くの感想がありました。
介護の本質について、これまでの歴史、企業と福祉の違い、一人ひとりの価値観や生活の捉え方を、多角的に学ぶ事ができました。専門性についての疑問も、田中先生より事例を通して分かりやすくご指導を頂きました。これまでになかった知識を学び、介護の専門性はご利用者や事業所ごとに異なることを知り、仕事の奥深さや重要性を理解することができました。
田中教授、感染対策が問われるなか、4ヶ月(15回30コマ)研修いただき誠にありがとうございました。今回の学びを糧に、よりよい支援を目指して専門性を向上してまいります。
コロナウィルス感染対策を考慮し、リモートでの研修を開催させて頂きました。








