新入社員社内研修 第2回
バイタルサインと身体観察
第2回社内研修、古城裕喜講師より「バイタルサインと身体観察」についてご講義を頂きました。今回の研修では、「1.生理的機能低下を知る」「2.バイタルサインと関連する知識」「3.病気と介護のポイント」についてお話がありました。
老化について年齢を重ねると、どんな変化があるか?新入社員からは「目が見えにくくなる」「耳が聞き取りづらくなる」などの老化に伴う変化について意見がありました。古城講師より高齢期の生理的特徴として、感覚機能の変化として味覚閾値が上昇し、塩辛い物や濃い味の物を好むようになります。・消化・吸収機能の変化では、消化酵素の活性や粘液などの分泌量、消化管蠕動運動が低下する。咀嚼・嚥下機能の変化として、唾液分泌量、嚥下反射の低下→嚥下機能の低下→誤嚥に繋がる恐れがありますとお話がありました。


一般的な特徴では環境・状況変化に順応が難しく、気温や衣類など環境に影響を受けやすくなります。古城講師より感じる力「観察の五感」視・聴・触・臭(覚)・違和感を活用し『なんだか何時もと違う』・いつもより活気がないな・身体がいつもより傾いているな・表情がいつもとちがうな、などの気付く力が大切になりますとご指導いただきました。体調に変化が見られる時には、バイタルサインに注意が必要です。「バイタルサインを測定しましょう」と言われたときに何を測定すればよいのか、体温・血圧・脈拍・呼吸状態を計測し、もう一つは「今日の調子はどうですか」と声を掛けながら意識状態も確認する必要があります。声を掛ける事によりいつもと違う様子でないか、これが気付きに繋がります。注意するべきことは、バイタルサインは数値だけ記録を取るのではなく、いつもの様子に変化がないかを確認し、いつもと違う様子に気がついたら、きちんと記録、報告を忘れず行う事が重要となりますとご指導いただきました。数値に見えない所が全身状態、意識状態の確認になりますので、必ず一つ一つ声を掛けながら今日の様子を確認することが大切です。高齢者の身体の特徴を理解し、測定基準値に異常がある場合には経過観察はもちろんですが、必ず看護師や介護リーダーへ報告し職員間での情報の共有を行う事が求められます。発熱がある場合には発熱の要因がどこにあるのか?感染・脱水・うつ熱など状態に応じて症状の原因を考える事も大切です。
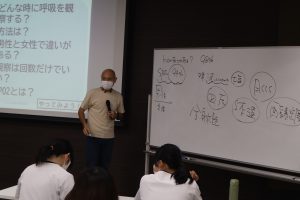

高齢者の全身状態の確認では、痛みに対し骨折についての知識も大事になります。オムツ交換を行う際に、身体を伸ばす事が出来ない身体の拘縮が強い利用者様の身体の動かし方や、どの様な身体の動かし方が適切かなどのお話がありました。今回は実践を交えて、専門職の理学療法士の助言をもらい介助を行う際に骨折をさせない介助方法や、気を付けるポイントについて学ぶ事が出来ました。高齢者はピンと腰を伸ばす事が出来ず、背中が曲がってきている方を目にします。これは骨粗鬆症の症状が進み骨折しやすい状態にあります。身体の状態や痛みの訴えに対してどこに骨折の恐れがあるか、また、骨折しやすい部位はどこか理解しておかなければいけません。


今回の研修では、利用者様の状態の変化においての知識を深める事が出来ました。利用者様によっては、言葉で伝える事が出来る方もいらっしゃれば、言葉では伝える事が出来ない利用者様もいらっしゃいます。生活支援員は言葉だけでなく、身体の様子や表情を見ながら体調確認も必要とされる為、普段と違う様子の変化に気付く事が出来るように、多くの関わりを持ちながら研修で学んだポイントを大事に小さな変化に気が付けるように取り組んでいきます。専門職としての知識や介護技術の向上を目指し、より質の高いサービス提供が出来るように頑張ります。
古城裕喜先生、本日は本当にありがとうございました。
※研修は受講者の体調・体温・接触管理・ワクチン接種・手指消毒等、室内換気も徹底して行っています。








