第4回 新入社員研修カリキュラム Web研修
第1部 「生活」について
 今回の研修は「生活」とは何か? というテーマでご講義いただきました。生活行為とは「人が生きていくうえで営まれる生活全般の行為」と定義されています。元気なときは、好きなことを自分で選択して実行できますが、加齢や病気により心身機能が衰えると、基本的な動作も不十分になり、身の回りのことができなります。新入社員の皆さんに「あなたの思う生活とは何か?」を発表いただき、専門職としてどの様な関わり方が適するのかを田中先生からご指導をいただきました。
今回の研修は「生活」とは何か? というテーマでご講義いただきました。生活行為とは「人が生きていくうえで営まれる生活全般の行為」と定義されています。元気なときは、好きなことを自分で選択して実行できますが、加齢や病気により心身機能が衰えると、基本的な動作も不十分になり、身の回りのことができなります。新入社員の皆さんに「あなたの思う生活とは何か?」を発表いただき、専門職としてどの様な関わり方が適するのかを田中先生からご指導をいただきました。

「生活と聞かれたら何と答えますか?」との田中先生の問いに、最も多い答えが「日常生活」でした。田中先生は、一般的に言う「食べる」「お風呂に入る」「寝る」は生活行為であると言われ、一つひとつの生活行為の束、この総体の束が「生活」であるとご説明いただきました。生活支援員は、生活のなかで出来なくなったことを見極め、適切な支援を提供する必要があります。いわゆる、適切さを見極めるチカラが専門職として重要になることを学びました。
適切な支援を見極めるには、会話の中から、困っているところ、生活が楽しくなるところ、幸せを感じるところを探り、生活の「快」につながる「何か」を検討する必要があります。人には自分なりの人生があり、価値観もそれぞれ違います。その人の価値観に寄り添い、「このように生きたい」という思いを理解しようと努力し続けることで、その人に適する支援がみえてきます。その人にとって満足いく喜びを提供することが、介護であり、生活支援であるとご指導頂きました。
第2部 「生活」について
介護で大切なのは、「生活」の「喜び」や「生きがい」を引き出すことです。田中先生から、「寝たきりの方の生きがい感は?」と尋ねられ、「寝ているばっかりで何もない気がします」と戸惑った場面がありました。田中先生は、そうした方の楽しみとして、「家族の方との面会はどうでしょう?」と問いかけられ、家族は親の元に集まる習慣を挙げて、お母さんが施設入所されている想定でご説明されました。お母さんが元気でいると、遠くの家族が施設に集まって来られます。家族が楽しく会話ができるのも、頑張っておられるお母さんのおかげになり、「そうか生きていればみんなが集まる希望になるのか、じゃあ来年もこうして頑張って生きて行こうかな」など、施設入所しているお母さんの意欲や生きがいにつながるかもしれません。些細な夢を創り、家族とつながることで、生きる希望になります。それを見い出せるか否かが支援者の腕の見せ所だとご指導いただきました。
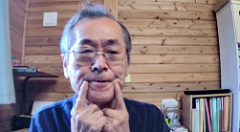 新入社員から、「笑顔を引き出すには、信頼関係が必要ですか?」という質問に、田中先生は、利用者は主人公であることが基本で、利用者が満足していただけるように、笑顔で接することが大切であるとご指導いただきました。利用者が「ムスッ」とした表情をされていると、笑うような声掛けを行うと良く、笑うような声掛けが、分からないときのために「笑うヨガ」の方法をご指導いただきました。相手がおかしくなくてもこちらが笑えば相手もつられて笑う技術です。口をすぼめて口角を上に上げ、眼を少し細くして、少しだけ歯が見えるように「ワハハハ」と笑えば相手もつられて笑います。と、田中講師の笑い声につられて新入社員のみなさんも思わずクスッと笑ってしまいました。
新入社員から、「笑顔を引き出すには、信頼関係が必要ですか?」という質問に、田中先生は、利用者は主人公であることが基本で、利用者が満足していただけるように、笑顔で接することが大切であるとご指導いただきました。利用者が「ムスッ」とした表情をされていると、笑うような声掛けを行うと良く、笑うような声掛けが、分からないときのために「笑うヨガ」の方法をご指導いただきました。相手がおかしくなくてもこちらが笑えば相手もつられて笑う技術です。口をすぼめて口角を上に上げ、眼を少し細くして、少しだけ歯が見えるように「ワハハハ」と笑えば相手もつられて笑います。と、田中講師の笑い声につられて新入社員のみなさんも思わずクスッと笑ってしまいました。

「笑うヨガ」は、落ち込んだ気持ちを高め、楽しい気分を周りに伝え、気分が高揚します。早々に取り組んで行きたいと思います。
今回のカリキュラムでは、生活をテーマに、多くをご指導いただきました。
生活について一人ひとりの「価値観」の違い、「普通」の捉え方の違いを学びました。新入社員の皆さんも自分の価値観にとらわれず、専門職としての視点で「快」を見い出す重要性を理解できたと思います。
田中教授、本日はありがとうございました。
コロナウィルス感染対策を考慮し、リモートでの研修を開催させて頂きました。








